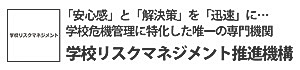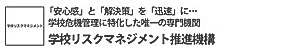教育現場におけるカスタマーハラスメントへの対応 / 鈴木彰典 元 校長
学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。
近年、教育現場において保護者や地域住民からの理不尽な要求や過剰なクレーム、威圧的な言動などが増加し、教職員の負担が大きくなっています。このような行為は「カスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」)」と呼ばれ、東京都では今年の4月からカスハラ条例が施行されました。本号では、カスハラの定義や具体例、適切な対応方法について解説しますので、教育現場の健全な運営を維持するための参考としてご活用ください。
◆カスハラの定義
東京都のカスタマーハラスメント防止条例におけるカスタマーハラスメントの定義は、「顧客等が就業者に対して著しい迷惑行為を行うこと。」とされています。この「顧客等」には保護者が、「就業者」には教職員が該当します。
◆教育現場におけるカスハラの具体例
次のような行為がカスハラに該当する可能性があります。
①教職員に対する暴言や侮辱的な発言
- こんな教師がいるから学校のレベルが下がる
- こんな簡単なこともできないのか、無能だ
②教職員に対する威嚇的な行動
- 机越しに教職員を睨みつける、大声で怒鳴る
③長時間の拘束や不当な謝罪要求
- 職員室や会議室で何時間も居座る
- 何度も全校生徒の前での謝罪を求める
- 「校長も一緒に謝りに来い」と要求する
④過剰で執拗な問い合わせや要求
- 一日に何度も同じ内容の電話やメールを送る
- 業務時間外や深夜に連絡し、即時の回答を要求する
⑤不適切な贈答品の強要
- 高価な贈り物を受け取るよう圧力をかける
⑥教職員に対するプライバシー侵害
- 家族構成や住所を執拗に尋ねる
⑦SNSやインターネット上での誹謗中傷
- 教職員の写真を無断で投稿し、名誉を毀損する発言を行う
⑧教育活動の妨害を目的とした苦情や要求
- 授業中に不必要に教室を訪れ、活動を中断させる
⑨重大な結果を招く虚偽の情報提供
- 事実と異なる情報を流布し、学校や教職員の信用を傷つける
⑩教職員への身体的接触や威圧的な態度
- 教職員の腕を掴む、押しのける
⑪無断で学校施設を訪問し、業務を妨げる
- アポイントなしで職員室などを訪れ、業務を妨害する
⑫退去要請に応じない行為
- 学校側が退去を求めても応じず、施設内で居座り続ける

◆カスハラ対応方針の策定(保護者・閲覧者向け)
学校(園)は、教職員が安心して教育活動に専念できる環境を提供するとともに、児童生徒等の健全な成長を支援する役割を担っています。そのため、保護者や関係者に向けて学校(園)におけるカスハラ対応方針を公表し、相互の信頼関係を築くことが重要です。
①カスハラ対応方針の目的
- 教職員が安心して働ける環境を確保する
- 保護者や関係者と健全なコミュニケーションを促進する
- カスハラ行為を未然に防止し、発生時には適切に対応する
- 教職員の負担を軽減し、教育の質を向上させる
- 児童生徒等に、より良い教育環境を提供する
②問題行動への対応
カスハラ行為が確認された場合には、以下の対応を行うことをカスハラ対応方針に明記します。
- 行為者への注意喚起
- 必要に応じて警察や弁護士と連携
- 問題が解決しない場合、立ち入り禁止措置や法的対応を検討
- 被害を受けた教職員の精神的ケアを優先し、必要に応じて専門カウンセリングを提供
③カスハラ対応方針の周知
学校(園)だより、学校(園)ホームページ、保護者説明会などを通じて広く周知します。
④見直し
法律や条例の改正、学校(園)を取り巻く環境の変化に応じて適宜見直しを行います。
◆カスハラへの適切な対応策
①初動対応の原則
カスハラ発生時には、以下の原則に従って対応することが重要です。
- 一人で対応せず、必ず複数人で対応する
- 学校(園)の方針に基づいて毅然と対応する
- 対応時間を決め、長時間の拘束を防ぐ
- 対応記録を必ず残す(日時・内容・対応者など)
②外部機関との連携
カスハラが激化した場合は、状況に応じて警察や関係機関に相談・通報する。
カスハラは、教育現場の健全な運営を損なう重大な問題です。教職員が安心して働ける環境を整え、一貫した対応を取ることで、教育の質を維持していただけたらと思います。
令和7年度が始まりました。本号でお伝えしましたが、カスハラ防止条例が施行される自治体がありますので、厚生労働省や自治体から公表されております「カスハラ防止に向けたマニュアル」を参考にされると良いと思います。これまでと比べると、保護者クレーム対応に一定の歯止めをかけることが可能になりますが、カスハラ防止への理解が定着するまでは対応に苦慮することも予想されます。
当機構は、今年度も皆様の学校(園)の支援に努めて参りますので、何かお困りのことがございましたら、遠慮なくご連絡をお願いいたします。また、保護者クレーム対応をはじめとする研修会(教育委員会・校長会・教頭会(副校長会)・私学団体主催並びに校内研修など)も承りますので、研修会を計画されているようでしたら、随時、ご連絡をお願いいたします。
今年度、皆様の学校(園)がさらに発展されますことを心より願っております。今年度もよろしくお願い申し上げます。
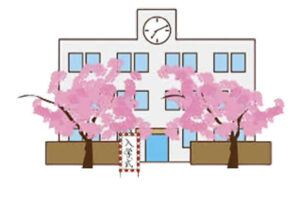
※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。
編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典